こんにちは、アウトドア大好きブロガーのユウタ(@yu_taok1)です。
自分は、既に10年以上、プランター栽培や、土地を借りて家庭菜園をしています。
プランター栽培も手軽で面白いですが、やはり畑で野菜作りをすると、野菜の成長も早く、作業の自由度も高いのでやりがいがあります。
さて、今回の記事では連作障害について書こうと思います。
プランター栽培だと、連作障害を意識しない方も多いかもしれませんが、実はとても重要です。連作障害を気を付けるかどうかで、生育や収穫量に大きな差が出てきます。
この記事では、連作障害とは何か、どんな影響があるのか、野菜の種類でどのように違うのか、そして連作障害の防ぎ方について紹介しようと思います。

連作障害を防ぐことは家庭菜園でとても重要になります。
必ず覚えておきましょう。
この記事が、家庭菜園を行っている方、新しく始めようとしている方のためになり、沢山収穫できれば幸いです。
本格的に土地を借りて、野菜を栽培したい場合は、「畑のレンタルサービス」のシェア畑が有名です。

シェ畑は全国に70農園あり、手ぶらで行くことができ、菜園アドバイザーが野菜作りについて教えてくれます。始めて家庭菜園を行う人は、最初はこういったサービスを利用するとすぐにレベルアップすることができます。

連作障害とは

連作障害は同じ場所で同じ種類の野菜を育てる事によって、病気になったり、生育が悪くなったりする事をいいます。同じ場所で栽培を控えた方が良い期間が、野菜毎に決まっています。
ほぼ全ての野菜が連作出来ないので、同じ場所で育てずに栽培場所を毎年ずらす(輪作:りんさく)を行うことが基本になります。
また、連作障害は同じ野菜を連続して作ることもそうですが、「同じ科」の野菜を連続して作っていても起こるので、注意が必要です。
例えば、エンドウを育てた場所では3~5年程は同じマメ科を育てない方が良いです。
「同じマメ科」というのは、枝豆など他のマメ科でも連作障害が出やすいので「同じ種類の野菜=同じ科の野菜」の栽培をしないようにしましょう。
家庭菜園のスペースは狭いため、連作障害だけ考えていると育てたい野菜を育てられなくなります。
連作障害が出にくいように土作り・土壌消毒など色々な方法を組み合わせつつ、栽培場所を変える(輪作)ようにしましょう。
また、プランター菜園であれば、同じ土で同じ科の野菜を栽培しないようにしたり、後ほど説明する土壌消毒などが有効です。
連作障害の原因とは

同じ場所に同じ野菜、同じ科の野菜を栽培するとなぜ連作障害が発生するのでしょうか。
大きく分けて3つの理由が原因と言われています。
土壌中の病害
土の中には多くの微生物が生息しており、中には病気を引き起こす病原菌も存在します。
一方で、植物は根から微生物の餌となる有機酸や糖、アミノ酸などを分泌しています。同じ科の植物は似た物質を分泌するため、連作するとそこに集まってくる微生物の種類も偏ってきます。
そのため、生物の多様性が崩れ、特定の病原菌だけが増えていき、土壌病害が発生しやすくなります。
連作障害で代表的な土壌病害には、次のようなものがあります。
青枯病 萎黄病 つる割病 根こぶ病 半身萎凋病
線虫による病害
線虫というと、野菜の根に寄生してこぶを作ったり、根を腐らせたりする「ネコブセンチュウ」や「ネグサレセンチュウ」などがあります。
線虫の中にはこのような悪い種類もいれば、それをやっつけてくれる良い種類もいます。
しかし、連作をすると土の中の環境が崩れてきて、線虫のバランスが崩れ、線虫害が起きやすくなります。
生理障害
野菜は種類ごとに必要な栄養成分が異なり、生育に消費するため、絶えずそれを必要とします。
そのため、連作をすると土の中の特定の養分が過剰になったり不足したりしてきます。
その結果、生理障害が起きやすくなったり、野菜の体力が低下して病害虫の被害を受けやすくなったりします。
連作障害の出やすい野菜と輪作年限
連作障害は全ての野菜で発生するわけではなく、連作障害が発生しやすい野菜と、発生しにくい野菜があります。
また、連作障害を避けるために、1度作った場所ではしばらく同じ種類・同じ科に属する野菜は作らずに、栽培間隔をあけるべき期間、「輪作年限」というものがあります。
それぞれの野菜の輪作年限は次のようになります。
「連作を気にしなくてよいか」のついては、×は必ず気を付ける、△は気をつける、○はそれほど気にしなくてもよい、◎は気にしなくてよい、という意味になります。
| 野菜名 | 科目 | 種類 | 栽培期間の間隔 | 連作を気にしなくてよいか |
| イチゴ | バラ科 | 果菜類 | 2~3年 | △ |
| トマト | ナス科 | 果菜類 | 3~4年 | △ |
| ミニトマト | ナス科 | 果菜類 | 3~4年 | △ |
| ピーマン | ナス科 | 果菜類 | 3~4年 | △ |
| パプリカ | ナス科 | 果菜類 | 3~4年 | △ |
| シシトウ・唐辛子 | ナス科 | 果菜類 | 3~4年 | △ |
| ナス | ナス科 | 果菜類 | 3~4年 | △ |
| ゴマ | ゴマ科 | 果菜類 | 0~1年 | ◎ |
| キュウリ | ウリ科 | 果菜類 | 3~4年 | △ |
| ズッキーニ | ウリ科 | 果菜類 | 0~1年 | ◎ |
| ゴーヤ | ウリ科 | 果菜類 | 2~3年 | △ |
| カボチャ | ウリ科 | 果菜類 | 0~1年 | ◎ |
| スイカ | ウリ科 | 果菜類 | 4~5年 | × |
| メロン | ウリ科 | 果菜類 | 3~4年 | △ |
| エンドウ | マメ科 | 果菜類 | 4~5年 | × |
| インゲン | マメ科 | 果菜類 | 1~2年 | ○ |
| エダマメ | マメ科 | 果菜類 | 3~4年 | △ |
| ラッカセイ | マメ科 | 果菜類 | 2~3年 | △ |
| ソラマメ | マメ科 | 果菜類 | 3~4年 | △ |
| オクラ | アオイ科 | 果菜類 | 2~3年 | △ |
| スイートコーン | イネ科 | 果菜類 | 0~1年 | ◎ |
| ブロッコリー | アブラナ科 | 葉菜類 | 2~3年 | △ |
| キャベツ | アブラナ科 | 葉菜類 | 2~3年 | ○ |
| ハクサイ | アブラナ科 | 葉菜類 | 3~4年 | △ |
| コマツナ | アブラナ科 | 葉菜類 | 0~1年 | ◎ |
| ホウレンソウ | アカザ科 | 葉菜類 | 1~2年 | ○ |
| 葉ネギ | ネギ科 | 葉菜類 | 1~2年 | ○ |
| 長ネギ | ネギ科 | 葉菜類 | 1~2年 | ○ |
| ニラ | ヒガンバナ科 | 葉菜類 | 3~4年 | △ |
| シュンギク | キク科 | 葉菜類 | 0~1年 | ◎ |
| レタス | キク科 | 葉菜類 | 3~4年 | △ |
| サニーレタス | キク科 | 葉菜類 | 1~2年 | ○ |
| サンチュ | キク科 | 葉菜類 | 1~2年 | ○ |
| ニンニク | ユリ科 | 葉菜類 | 1~2年 | ○ |
| 行者ニンニク | ユリ科 | 葉菜類 | なし | ◎ |
| ラッキョウ | ユリ科 | 葉菜類 | 1~2年 | ○ |
| アスパラ | ユリ科 | 葉菜類 | 3~4年 | △ |
| タマネギ | ユリ科 | 葉菜類 | 3~4年 | △ |
| ミツバ | セリ科 | 葉菜類 | 1~2年 | ○ |
| セロリ | セリ科 | 葉菜類 | 0~1年 | ◎ |
| クウシンサイ | ヒルガオ科 | 葉菜類 | 1~2年 | ○ |
| モロヘイヤ | アオイ科 | 葉菜類 | 1~2年 | ○ |
| シソ | シソ科 | 葉菜類 | 1~2年 | ○ |
| エゴマ | シソ科 | 葉菜類 | 1~2年 | ○ |
| ニンジン | セリ科 | 根菜類 | 2~3年 | △ |
| サツマイモ | ヒルガオ科 | 根菜類 | 1~2年 | ○ |
| カブ | アブラナ科 | 根菜類 | 1~2年 | ○ |
| ラディッシュ | アブラナ科 | 根菜類 | 1~2年 | ○ |
| ダイコン | アブラナ科 | 根菜類 | 3~4年 | △ |
| ジャガイモ | ナス科 | 根菜類 | 4~5年 | × |
| ゴボウ | キク科 | 根菜類 | 4~5年 | × |
| ナガイモ | ヤマイモ科 | 根菜類 | 3~4年 | △ |
| ジネンンジョ | ヤマイモ科 | 根菜類 | 3~4年 | △ |
| ショウガ | ショウガ科 | 根菜類 | 4~5年 | × |
| ミョウガ | ショウガ科 | 根菜類 | 1~2年 | ○ |
| パセリ | セリ科 | ハーブ | 1~2年 | ○ |
| パクチー | セリ科 | ハーブ | 1~2年 | ○ |
| バジル | シソ科 | ハーブ | 1~2年 | ○ |
| ルッコラ | シソ科 | ハーブ | 1~2年 | ○ |
野菜の種類をみながら、輪作年限に注意をするようにしましょう。記載している期間は同じ場所での栽培期間を空けるようにすることが大事です。
連作障害を防ぐ方法

それでは、連作障害を防ぐ方法について紹介します。
輪作
連作障害を防ぐ基本は、同じ場所で同じ野菜を続けて作らずに、異なる科の野菜を順番に作っていく「輪作」を行うことです。
違う科の野菜を作ることで、土の中の環境が偏らず、土壌生物相・微生物相が豊かになって、連作障害が起きにくくなります。
1~2苗しか育てられない本当に狭いスペースだと出来ませんが、ある程度の面積があれば5区画に分けて野菜の栽培計画をたてるとうまく順番に場所を変えられる方法です。
先に区画を分けて、育てる種類を豆類・果菜類・葉菜類・根菜類・永年作物の5種類にわけてローテーションし、5年分の計画を立てることになります。
間作・混植・コンパニオンプランツの活用
順番に違う科の野菜を作る「輪作」を同時に行ってしまおうというのが、複数の野菜を一緒に植える「間作・混植」という方法です。
間作は、作物と作物との間に他の作物を植える方法。混植とは株間などに他の作物を混合栽培する方法。
また、近くに植えることで、病害虫の発生を防いだり、生育が良くなったりと、お互いに良い影響を与える植物を「コンパニオンプランツ」と呼びます。
例えば、連作障害で被害のでる「センチュウ」を少なくする効果がマリーゴールドにはあるといわれています。マリーゴールドを同じ畝(うね)に植えておき、野菜の栽培終了した時に一緒に土の中にすきこむと効果があると言われています。
その他にも、ミニトマトとバジルを一緒に栽培すると良いというのも有名です。
色々なコンパニオンプランツが存在します。
有機たい肥を使う・有機物を土に入れる
畑の土の中には目には見えない微生物がたくさんいます。この微生物は有機物を入れると分解するために増えますが、連作障害が出る畑では病気を発生させる悪い微生物が増えている状態になっています。
そのため、良い微生物を増やす事で、悪い微生物の活動が抑制されて病気の発生が出にくい状態になります。
良い微生物を増やす為には、緑肥作物や堆肥などの有機物を土壌に投入すると微生物が増えて効果的です。
完熟堆肥などの有機堆肥を使用するのが最も効果的で、栄養も含まれていておススメです。
有機堆肥は団粒化を促し、土の隙間が多くなり通気性や排水性がよくなり、これにより、土壌中の有用微生物の活動を活発化させ、微量要素の補給を行います。
土壌消毒を行う
土壌を消毒する方法も効果的です。
土壌消毒には、
- 太陽熱消毒
- 土壌還元消毒
- 土壌消毒剤(農薬)
の方法があります。
簡単に説明すると、
「太陽熱を利用した天然の消毒方法」と、「農薬を使った消毒方法」になります。
土壌消毒を行う場合は、周りへの影響、土壌中の環境を考えると、太陽熱消毒又は土壌還元消毒をおススメします。
プランター栽培の場合は、夏の暑い日に沸騰したお湯をかけ、透明のごみ袋を被せると短時間で熱消毒が可能です。
土壌消毒に関する記事はコチラ👇
ネギ類を植える
ネギ類の野菜は連作障害をおこしにくいばかりか、地中の病害虫の活動を抑制する効果をもっています。
この為、ネギやニンニク、ニラといったネギ類の野菜を輪作のローテーションに組み込む事により連作障害をおこしにくくする効果が期待できます。
抵抗性品種・接ぎ木苗を使う
土壌病害に対して、抵抗性のある品種を選びます。
例えば、根こぶ病に抵抗性のある品種には「CR」、萎黄病に抵抗性のある品種には「YR」の文字が付けられています。
また、キュウリ、スイカ、トマトなどの苗を選ぶ際は、「接木苗」のものを選ぶようにしましょう。台木に病気に対する抵抗性品種が使われており、病害虫に強い苗になっています。。
【まとめ】連作障害を防いで上手に野菜を栽培しよう

今回は、連作障害について記事を書かせていただきました。
連作障害を防ぐ方法ですが、やはり一番大事なことは、連作障害が起きやすい野菜の相性を事前に知り、適切に輪作を行うことです。
病害虫防止のために、接ぎ木苗を購入する人は多いと思いますが、野菜によっては苗の植え付けでなく、種から栽培することもあります。
連作障害の起こらない野菜の組み合わせを調べるとともに、過去どの場所で何を栽培したかを記録しておき、今後の栽培計画を組み立てることが大事です。
本日の記事は以上になります。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。


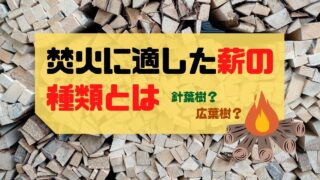


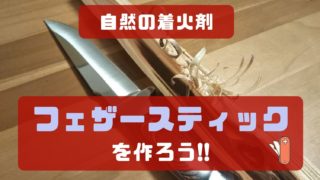



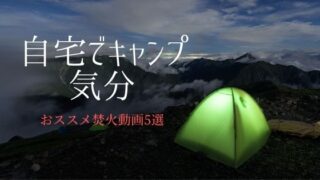






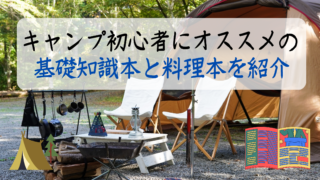









コメント